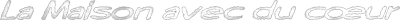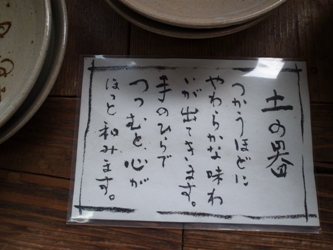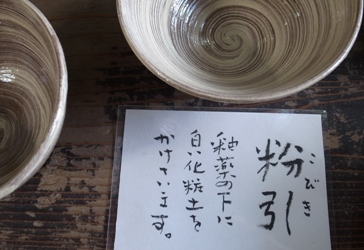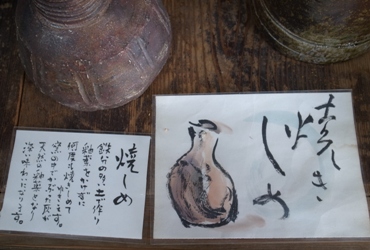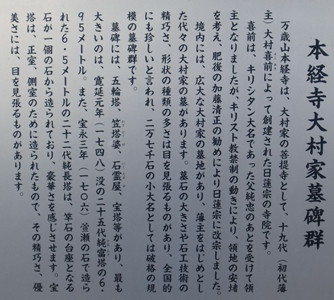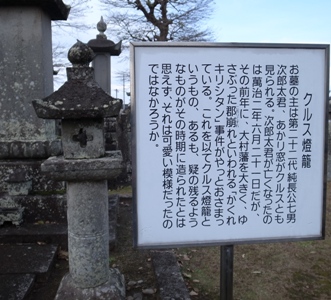三重県・四日市、土屋さんのオーダーのサイドボードが 形になってきつつあります。
使用目的は TVボードなのですが 従来のTVボードのようにガラス扉で中の機器類を見せる
タイプのものではないため どちらかというと サイドボードと言った方がよいのでしょう。
用材は 北米産のポンデロサパイン 20mm厚の無垢材を基本に使用しています。
長期的に見て 湿気や乾燥等の影響による変化を発生させないように タテ・ヨコの接合部は
彫り込み、はめ込むような構造にしています。 多少の手間は必要ですが 狂いのない組み立てに
仕上がります。

本体の組立てには最も神経を使います。 全ての個所が直角になっていないと いろんな所に
狂いが生じてきます。 後で 引出し・扉等がピタッと収まるように あらゆる個所のチェックを
確実にしていかなければ 後で余計な苦労をすることになってしまいます。
ハタガネやクランプは第二・第三の腕となって 確実な力になりますが 力関係を甘く見ると
取り返しのつかないような失敗も ・・・・



いつもの事ですが デザイン画はあっても 細かな寸法を書きこんだような図面などは 全く存在
しません。 資料として残せば 次に生かせ楽なのですが 制作を依頼して下さった方だけの為に
創っていますので 次に同じデザインを引用することを あえて出来なくしています。
その都度 デザインを考え出すのはかなりのエネルギーを使い大変なのですが 最近では それが
楽しみにもなっているのは なぜなのでしょうか。


このサイドボードの一番の特徴は 全体を支える かわいい丸脚です。
脚のデザインを猫足にしょうと考えていましたが 高さの設定がある中では 本体の容積に
影響することもあったり また 幅が1850mmサイズですので 全体のバランスを考え
丸脚を選択してもらいました。

前部モールデザイン

わん曲しないように創られた 棚板